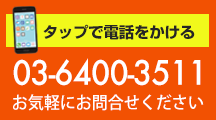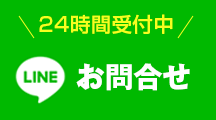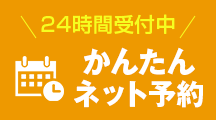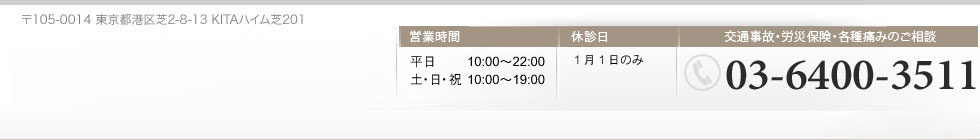Blog記事一覧 > 運動習慣 | 芝公園・浜松町・赤羽橋・三田 芝公園整骨治療院 - Part 2の記事一覧
こんにちは。芝公園整骨治療院の藤本です。
前回(2022年9月10日)、『運動脳』(アンデシュ・ハンセン/サンマーク出版)という本を紹介しました。
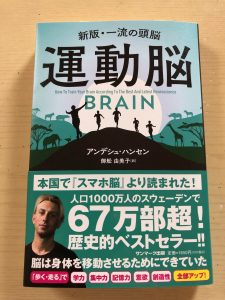
「運動習慣」に対する意識をより高く持って頂けるように、
「運動習慣」が「脳」に対して、「何故」、「どのように」良いのかについての具体的な例を、
本書の中から少し紹介したいと思います。
例えば、私たちの身体(細胞)は日々代謝を行っています。
その過程で発生する『キヌレニンという代謝物質は脳に害を及ぼすが、筋肉中の成分によって無害化されると脳に到着できなくなる』そうです。『要するに筋肉が、機能障害を誘発するストレス物質を取り除く処理工場として働く』のだそうです。
つまり、『肝臓は血液に含まれる有害物質を除去して血液をきれいにするが、筋肉も同じような働きでストレスから脳を守っている』のだそうです。(『』は本書からの引用)
また、『主に大脳皮質(脳の外層部)や海馬で合成されるタンパク質』である『BDNF(脳由来神経栄養因子)』は、『脳神経が他の物質によって傷ついたり死んだりしないように保護している』と同時に、『新たに生まれた細胞を助け、初期段階にある細胞の生存や成長を促す役目』や、『脳の細胞間のつながりを強化し、学習や記憶の力を高め』る働き、そして『脳に可塑性を促して細胞の老化を遅らせる働きもしている』そうです。
この『BDNFの生成を促すのに、運動ほど効果的なものはない』そうです。
さらには、『海馬は記憶の中枢という仕事以外にも、感情を制御したり、空間を認識したり、過去に訪れた場所を見つけたりするといった重要な仕事をしている』が、
『運動によっても、海馬の細胞新生を促すことができる、というより、運動ほど脳細胞の新生を促せるものはないといっていい』そうです。
分かりやすい例を挙げれば、『毎日、意識的に歩くと認知症の発症率を40%減らせる』そうです。
どうですか?「身体を動かさなくては!!」という気持ちになってきましたか?
もちろん闇雲に運動すればするほど良いという訳ではなさそうです。
先日(8月13日)このブログでも、「筋トレもやり過ぎには注意(!?)」というデータを紹介しましたが、
本書でも、(少なくとも脳に対しては)『疲労を覚えるほど運動すると、かえって逆効果になる』と言っています。
これは、運動すると脳に流れ込む血流が増え、それによって脳の働きが促進されるが、疲れるほど運動すると、筋肉により多くの血液が必要になり、血液が脳から筋肉へと流れを変えて、脳の血流量は逆に減るためのようです。
かと言って、あまりにも軽くこなせる程度の運動では「運動」の内に入らないですが、
そのあたりの、どのような、そして、どの程度の運動が適当かも含め、
本書には、様々な症例やデータに基づいたお話が語られていますので、
ご興味を持たれた方は、是非ご一読ください。
芝公園整骨施術院・鍼灸院・整体院
〜首、肩、腰の痛みや交通事故施術〜
スタッフ全員が経験豊富な国家資格者です♪
お気軽にお問合せ下さい♪♪
東京都港区芝2-8-13KITAハイム芝201
03-6400-3511
こんにちは。芝公園整骨治療院の藤本です。
『いくつかの大規模な研究によると、運動の習慣があると、新型コロナウィルスに感染しても入院して集中治療を受けるリスクが50%減る。』と聞くといかがですか?
もちろん『ウィルスに感染しないわけではないが、感染したとしても重症化したり亡くなったりするリスクが減る』というのです。
これは、最近日本で出版された『運動脳』(アンデシュ・ハンセン著/サンマーク出版)という本の中に紹介されていることです。
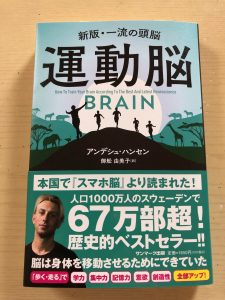
本書は、以前このブログでも紹介した『スマホ脳』、『最強脳』の著者で精神科医・アンデシュ・ハンセンの著作です。
母国スウェーデンでは『スマホ脳』より読まれたとか。
『スマホ脳』、『最強脳』は、スマホが如何に「脳」に悪影響を与えるかということと、その対策はまさに「運動」だ、という内容でした。
(※各々の本の紹介については、2021年4月21日、2021年12月3日のブログをご参照ください)
本書の主な内容も、やはり、「脳」に対して「運動」が如何に大切か、如何に良い影響を及ぼすか、ということです。
『運動は不安障害やうつ病のリスクを減らすだけでなく、それらを治療する手段として抗うつ剤やセラピーに匹敵する効果があり、その事実はもはや動かしようがない。』
『身体を動かすと、気分が晴れやかになるだけではなく、あらゆる認知機能が向上する。記憶力が改善し、注意力が研ぎ澄まされ、創造性が高まる。それどころか知力にまで影響が及ぶ』といったことが具体的に紹介されています。(『』は本書からの引用文)
そして、「運動」が、
何故、どのように、精神疾患に効果を発揮し、
何故、どのように、認知機能をはじめとする脳の機能に好影響を与えうるのか、
そしてどのような運動をすれば良いのか、
が具体的に語られています。
「運動」の効果の一つとして、冒頭に紹介したコロナへの効果が紹介されています。
専門的な内容が語られながらも、一般向けに、非常に読みやすく、分かりやすく語られており、読めば「運動」をしたくなる様な一冊になっています。
スマホなどのモバイルの急速な普及に加え、長引くコロナ禍で、身体的にも、メンタル的にも不調を覚える方が増えている昨今、
私個人的には、前著『スマホ脳』以上にオススメの一冊です!!
また日を改めて本書のもう少し具体的な紹介をしたいと思いますが、
興味のある方は是非ご一読ください!!
芝公園整骨施術院・鍼灸院・整体院
〜首、肩、腰の痛みや交通事故施術〜
スタッフ全員が経験豊富な国家資格者です♪
お気軽にお問合せ下さい♪♪
東京都港区芝2-8-13KITAハイム芝201
03-6400-3511
こんにちは。芝公園整骨治療院の藤本です。
前回、前々回と熱中症の分類と症状、その対処法についてお話しました。
今回は、熱中症対策について、ちょうど一年前に紹介したブログの内容を再度紹介したいと思います。
先ずは、熱中症予防対策としての適度な発汗習慣についてです。
この時期なんとも不快な汗ですが、発汗の大切な作用のひとつに
カラダから水分が蒸発することによって
上昇した体温を下げ、体温調節を行うという働きがあります。
汗は、汗腺から分泌されます。
この汗腺、実は、体表にあるすべての汗腺が常に働いている訳ではありません。
その働きをお休みしている休汗腺が一定の割合存在していると言われています。
しかし、常に空調などで調節された快適過ぎる(?)空間に居て汗をかく機会が少なく、
加えて、運動習慣が無く、定期的に適度な発汗をする習慣が無い様な人は、
この休汗腺が増えてしまうと言われています。
そうなるとどうでしょう?
体温が上昇し、いざ汗をかかないといけない状況になった時に上手く汗をかけず、
適切な体温調整、つまりクールダウンが出来辛くなります。
つまり、熱中症になる要因の一つには、気温や湿度などの外界の条件の他、
カラダが上手く体温調整できなくなっていることもある様です。
昨今、マスク着用により、適度な口からの体温放出も出来難くなっています。
ですから、普段から適度に汗をかいて、体温調整が上手く出来るカラダ作りをしておく必要があります。
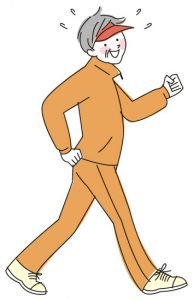
その為には、極端に冷房のきいた部屋に一日中閉じこもらないこと、
適度に運動をして適切な汗をかく習慣をつけること、
などを心がけてください。
もちろん汗をかく際には、水分補給に注意し、脱水症状にならないよう気を付けましょう。
汗をかいた後はこまめに着替え、汗が引いた後にかえって身体を冷やさない様にも気を付けてください。
汗は吸水性の良いタオルでそっと押さえて吸い取るようにし、
ゴシゴシ擦って毛穴が汚れで塞がれない様にしましょう。

適度な発汗は大切ですが、汗のかき過ぎもまた注意です。
中医学では、汗は“透明の血液”とも呼ばれ、極端な、もしくは異常な発汗は
大出血したことにも等しい体力の消耗を招くと考えます。
快適過ぎる(?)お部屋に閉じこもり過ぎず、
適度に運動して、適度に汗をかき、
感染対策に気を付けながらも、汗腺を活動させておきましょう!!
芝公園整骨施術院・鍼灸院・整体院
〜首、肩、腰の痛みや交通事故施術〜
スタッフ全員が経験豊富な国家資格者です♪
お気軽にお問合せ下さい♪♪
東京都港区芝2-8-13KITAハイム芝201
03-6400-3511
こんにちは。芝公園整骨治療院の藤本です。
皆さん、日常での立ち姿勢、座り姿勢などの習慣にどれくらい気を配っていらっしゃいますか?
前回、『ロジカル筋トレ』(清水忍著/幻冬舎新書)という本を紹介しましたが、
その中に、興味深い記述があったので、引用して紹介させて頂きたいと思います。
それは、イチロー選手に関する記述です。
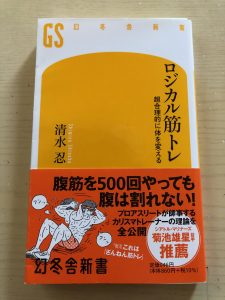
『大打者イチロー選手は、シアトル・マリナーズで活躍していた頃、球場のロッカーロームで硬いパイプ椅子にしか座らなかったそうだ。
メジャーのロッカールームでは選手たちがくるげるよう、座り心地のいいフカフカのソファーも用意されている。それなのに、なぜイチロー選手は常にパイプ椅子にしか座らなかったのか——。その理由は『フカフカのソファーよりもパイプ椅子のほうが、坐骨の支えで骨盤を立てて座れて、腰に負担がかからないから」だったそうだ。
つまり当時のイチロー選手は「椅子に座る」という日常的行動にも明確な根拠を求め、自身のコンディション低下やパフォーマンス低下につながりそうな要因をことごとく排除していたというわけだ。』(以上、『ロジカル筋トレ』(清水忍著/幻冬舎新書)より引用。太文字、文字の色変化はブログ筆者による)
いかかですか? さすがイチロー選手、といったところでしょうか。
私も患者さんにはよく座位姿勢(イチロー選手の記事にある通り、坐骨で座るということ)をアドバイスさせて頂くのですが、
現代人は大人から子供まで、座り姿勢の悪い人が多い様に感じます。
悪い姿勢が習慣化してしまうと、せっかく運動している時にも、習慣化した悪い姿勢が出てしまい、悪いフォームで運動してしまっている可能性があります。
そうすると、本書にもある通り、運動の効果が半減するだけでなく、反って体に負担をかけてしまう可能性があります。
トレーニングの際の正しいフォーム(姿勢)というのは当然大切なことですが、
正しいフォーム(姿勢)というのは日常動作での習慣こそ大切なのだと思います。
本書では、「腰痛には腰周囲の筋肉を鍛えると良い」という一般論に対しても、
腰を支える筋肉を付ければ良いという問題ではなく、(習慣的な)姿勢の問題だと言っています。
イチロー選手ほど厳格ではなくとも、健康の為には、或いは、健康の為に行う運動の効果を上げる為にも、
仕事中や日常生活での姿勢の習慣を少しだけ見直してみてはいかがでしょうか?
芝公園整骨施術院・鍼灸院・整体院
〜首、肩、腰の痛みや交通事故施術〜
スタッフ全員が経験豊富な国家資格者です♪
お気軽にお問合せ下さい♪♪
東京都港区芝2-8-13KITAハイム芝201
03-6400-3511
こんにちは。芝公園整骨治療院の藤本です。
皆さん、日常の動作が楽になる「体の使い方」を知れたら良いと思いませんか?
「正しい姿勢」、「正しい動き方」、
こうしたヒントを古武術から学ぼうという講座『古武術に学ぶ 体の使い方』が、NHK(総合、教育Eテレ)の『趣味どきっ!』で始まりました。
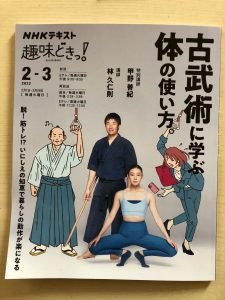
古武術というと何だか古臭い、現代人には縁の無い世界の様に感じますが、
ひと昔前、巨人の桑田投手復活の陰に古武術の稽古があった、という報道で注目を集めたことがあります。
その更に前では、王選手の一本足打法の完成に合気道の達人の指導があったことをご存知の方もいらっしゃると思います。
近年では、「古武術介護」などという言葉もあり、介護の現場で、介助の際に体に負担の少ない体の使い方が、古武術をヒントに生み出されています。
コロナ禍でおうち時間が増えている為か、患者さんからは、「運動不足」と「姿勢が気になる」というワードが良く聞かれます。
「運動不足」+「不良姿勢」は、肩凝りや腰痛の原因となり、血流も悪くなって疲れも抜けにくくなります。
日常的に動く機会が減り、運動不足だと感じていても、ジムなどに行くのは感染や人混みを気にする方もいます。
単純に外出がおっくうになってしまった方もいるでしょう。
その上、一日中家で座っている時間が長くなると、当然姿勢も悪くなりがちです。
そこに、運動不足による筋力低下も手伝って、増々正しい姿勢を維持し辛くなり、不良姿勢が習慣化。
こうして体が動き辛くなると益々運動不足に…、と、どんどん悪循環してゆきます。
この悪循環を打ち破るのは、先ずは、場所や時間を取らずに「お家で出来る運動」でしょう。
そして、「正しい姿勢」、「正しい動き」を行い維持する為に必要な運動です。
この講座ではそうした運動が紹介されています。
ご興味のある方は是非ご覧になってみてください。
健康のために、是非、体にとって楽な体の使い方を身に付けましょう!
もしも「テレビや動画、書籍の情報だけでは分かりにくい」という方や、「自力だけではどうしようもない」といった方は、是非当院まで!!
お身体に合わせた施術と同時に、個々のライフスタイル応じた日常生活でのアドバイスをさせて頂きます!!
芝公園整骨施術院・鍼灸院・整体院
〜首、肩、腰の痛みや交通事故施術〜
スタッフ全員が経験豊富な国家資格者です♪
お気軽にお問合せ下さい♪♪
東京都港区芝2-8-13KITAハイム芝201
03-6400-3511
こんにちは。芝公園整骨治療院の藤本です。
以前このブログで『スマホ脳』という本を紹介しました。
「スティーブ・ジョブズなどのIT業界のトップは自らの子供にはデジタル・デバイスを与えなかった」という事実と共に、
スマホが“脳”や“健康”に与える重大な影響について書かれていました(2021年4月21日のブログ参照)。
この本の反響を受けて、
“では、どうすれば良いの?”という問いに対するアンサーとして書かれたのが、
同著者による『最強脳』という本です。

『実は、この本の結論は一言で言えてしまいます。
運動をしよう—–そうすれば脳は確実に強くなる。』
日本語版の冒頭「日本の読者の皆さんへ」の中で、ハンセン先生がいきなりこう書いている通り、
この本の内容と結論はこの一点に尽きます。
ただ、大切なのは、“運動することによって、脳の中ではどのような変化が起きているか”、ということです。
前著『スマホ脳』では、スマホが“脳”や“身体”にどの様な影響を与えるかが書かれていましたが、
本書では「運動が子供や若者の脳にどのような影響を与えるかという知識を紹介」しています。
それと同時に「運動するモチベーション」が上がる様な知識の紹介もされています。
以前、『スマホ脳』を紹介した後に、『脳を鍛えるには運動しかない!!』という本も紹介しましたが(2021年5月11日ブログ)、
“身体”の健康のためだけでなく、“脳”のためにも、やはり“カラダを動かすこと”が一番良い様です。
本書でも、“カラダを動かすこと”は、
身体が強くなり、見た目もスッキリするだけでなく、
認知機能が高まり、発想力、記憶力、集中力も高まり、
気分も良くなって幸せな気分になり、
睡眠の質も改善されて、ストレスにも強くなる、と言っています。
皆さんがこの様にすこぶる健康になると、治療院としては少し困った面も出てくるかもしれませんが(笑)、
自身の為、是非、カラダを動かす習慣をつけて行きましょう!!
めざせ!健康長寿!!
芝公園整骨施術院・鍼灸院・整体院
〜首、肩、腰の痛みや交通事故施術〜
スタッフ全員が経験豊富な国家資格者です♪
お気軽にお問合せ下さい♪♪
東京都港区芝2-8-13KITAハイム芝201
03-6400-3511
こんにちは。芝公園整骨治療院の藤本です。
パソコンでの仕事が増えている上に、仕事以外でもモバイルに向かっている時間が多くなり、コロナ禍も手伝って、皆さん、座りっぱなしの時間がどんどん増えているのではないでしょうか?
一日に座位を取っている時間が11時間以上の人は、同じく一日4時間以下の人に比べて、死亡リスクが約40%高まるなどというデータがあります。
日本人の一日の平均座位時間は、世界最長の7時間だということですが、
長時間の座りっぱなしは、喫煙や飲酒と同様に、心筋梗塞、脳血管疾患、肥満、糖尿病、がん、認知症などの健康リスクが高まる、と言われています。
また、メンタル・ヘルスへの影響に関しても、一日の坐位時間が12時間以上の人では、同じく6時間以下の人の3倍のリスクがあるとの報告も見られます。
しかし、私がこれらのデータや研究報告を見ていて一番気になったのは、
上述の様なデータ、つまり「一日の座位時間が長いことによって引き起こされる健康リスク」が、
「運動習慣の有無にかかわらず」、あるいは「定期的な健康増進プログラムへの参加の有無にかかわらず」、上記の様な結果であるとされていたことでした。
つまり、定期的な運動を行っても、同一姿勢を続ける(≒動かない)時間が長いことによって生じるリスクは帳消しには出来ない、という訳です。
これは運動をしても意味がない、と言っているのではないでしょうし、
もちろん運動習慣は無いよりもあった方が、運動を行ったなりの健康メリットはあるはずです。
しかし、定期的に運動をしているからといって安心してはいけない、
カラダにメリットとなること(=定期的な運動)を行う一方で、
デメリットになる習慣(=長時間の座位)を減らさないと、そのリスクは高くなる、ということです。
とは言え、仕事で長時間の座位を余儀なくされている方も多いと思います。
仕事中は、せめてタイマーをかけてでも、時間を決めて定期的に立ち上がるようにしたり
(30分毎が理想ですが、現実的でなければ、せめて1~1.5時間に一度は座りっぱなしを解除して欲しいですね)、
座っている時も出来る限り負担の少ない正しい座位姿勢を習慣づけるなど、リスクを最小限にする工夫を行いたいものです。
また、お仕事で疲れているとは思いますが、
仕事以外の時間では座りっぱなしになる時間を極力減らす様にできれば良いと思います。
また、正しい座位姿勢を維持するのも、習慣づいていないとなかなか大変なことだと思いますので、
これもまた、お仕事で疲れているとは思いますが、
仕事以外の時間を利用して正しい座位姿勢を維持できるための体幹トレーニングを行うなどの対策ができると、
座位による健康リスクを下げると同時に、運動によるメリットを得る方法として良いのではないかと思います。
芝公園整骨施術院・鍼灸院・整体院
〜首、肩、腰の痛みや交通事故施術〜
スタッフ全員が経験豊富な国家資格者です♪
お気軽にお問合せ下さい♪♪
東京都港区芝2-8-13KITAハイム芝201
03-6400-3511
こんにちは。芝公園整骨治療院の藤本です。
皆さんは血液型占いや血液型による性格診断のようなものを信じますか?あるいは気にしますか?
海外ではあまり血液型による性格診断などは行われないようで、
「日本人は血液型の話しが好きだねえ」、というのが海外の人たちの感想だとか、そうでないとか・・・。
この血液型による分析(分類)、元々は、昔、日本に軍隊があった頃、
統率の取れた軍隊を編成するために、血液型による性格の傾向を調べた統計が起源になっている、
という話を聞いたことがあります(どこで聞いたのか、読んだのか、忘れましたが・・・)。
そして、これも元々はどこで聞いたのか(読んだのか)忘れましたが、
血液型による性格の傾向には医学的な根拠もある、という話も、聞いたことがありました。
例えば、O型は免疫力が高いため、狩猟に出ていた原始のころから、
病気やケガの心配をあまり気にせずに大胆に行動出来ていた為、大雑把、おおらかな傾向となり、
A型は免疫力がO型に比べて低い為、病気やケガに注意しながら慎重に行動する必要があったことから、
繊細で神経質な傾向となりやすい、といった事であったと記憶しています。
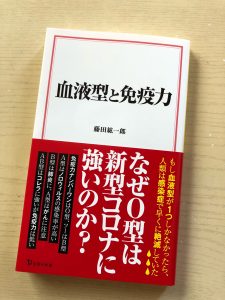
こうした血液型による違いを、免疫力の観点から、医学的に書いてあるのが、
腸の研究で有名な藤田紘一郎先生の『血液型と免疫力』(宝島社新書)という本です。
ざっくり言うと、
A型というのは血球にA型因子を持っていて、自分とは異なるB型因子に対する抗体(≒免疫力、抵抗力)があり、
B型は、血球にB型因子を持っているので、A型因子に対する抗体(≒免疫力、抵抗力)が、
O型は、自身がA型因子もB型因子も持っていないので(O型は元々は「ゼロ型」ということ)、A型、B型の両方に対して抗体(≒免疫力、抵抗力)がある、ということです。
ちなみにAB型は、自身の中にA・B両方の因子を持っているので、A・Bいずれに対する抗体も持っていません。
実は、人間以外の自然界のあらゆる生き物がこのABO型の因子を持っていて、
細菌や寄生虫などにもABO型があり、ウィルスにも種類によるABO型との相性の様なものがあるそうです。
(ちなみに細菌などにはA型因子を持ったものが多いそうです。あと、ウィルスは生物ではありません。)
つまり、ヒトは、持っているABO型の抗体の種類と数の違い(=血液型の違い)が
免疫力、抵抗力の違い(強さ)として現れる、ということの様です。
(以上、上記『血液型と免疫力』による)
とは言え、血液型には、ABO型以外にRh型の区別もありますし、
免疫力や抵抗力、個々の体力や回復力といったものは、
日常での運動習慣や食事、生活習慣などの後天的な要素に因るところが大きいことも確かです。
アドラーが『大切なのは何が与えられているかではなく、与えられているものをどう使うかである』と言ったように(8月25日ブログ参照)、
血液型による先天的な傾向はあるものの、それを知った上で、
それをどう生かして自身の免疫力を上げてゆくのかは、私たち自身の努力次第のようです。
同書では、血液型ごとのかかりやすい病気、かかりにくい病気などの他、
血液型ごとの相性の良い食べ物なども紹介していますので、
自身の傾向を知り、それに合った生活習慣の改善や強化の参考になるかも知れません。
免疫力が気になる昨今、興味のある方は、是非ご一読してみてください。
芝公園整骨施術院・鍼灸院・整体院
〜首、肩、腰の痛みや交通事故施術〜
スタッフ全員が経験豊富な国家資格者です♪
お気軽にお問合せ下さい♪♪
東京都港区芝2-8-13KITAハイム芝201
03-6400-3511