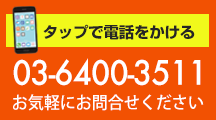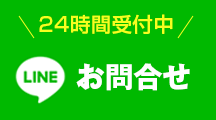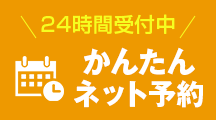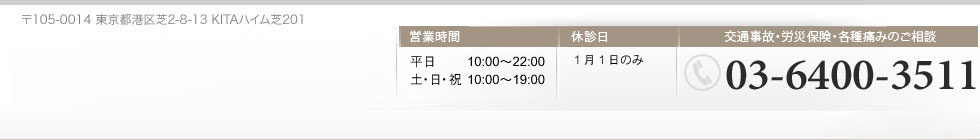Blog記事一覧 > スマホ脳 | 芝公園・浜松町・赤羽橋・三田 芝公園整骨治療院の記事一覧
こんにちは。芝公園整骨治療院の藤本です。
病院や治療院でストレートネックだと言われ、気になさっている方は少なくないと思います。
「ストレートネック」は、「スマホ首」などとも呼ばれ、デジタル機器を長時間使用し続ける際に不良姿勢が長く続くことで、本来あるべき頸椎の自然な湾曲が減少し、真っ直ぐ気味になってしまっていることです。
そして、この頸椎の自然な湾曲が無くなることが、頭痛や肩凝りをはじめとした様々な不調の原因になるとされています。
ただ、ひとつ認識しておかなくてはならないことは、既述の通り、ストレートネック(スマホ首)はデジタル機器を不良姿勢で長時間使用し続けることによって生じるものだということです。
決して、ストレートネック(スマホ首)だから、ついついスマホを長時間見てしまう、という訳ではないということです。
スマホの使い過ぎがストレートネックの原因であって、
ストレートネックがスマホ使い過ぎの原因ではないのです。
私などは、頭痛や肩凝りなども、ストレートネックであることが原因というよりも、ストレートネックになる様な習慣的な不良姿勢やスマホの使い過ぎ自体が直接原因ではないかと考えているくらいです。
とすると、ストレートネックやそれに伴う(とされる)身体の不調に対しては、スマホとの付き合い方を少し考え直さなくてはなりません。
そこで今回紹介したいのが、『脱スマホ脳かんたんマニュアル』(アンデシュ・ハンセン著/久山葉子訳/新潮文庫)です。
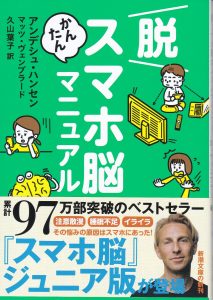
以前にこのブログで『スマホ脳』という本を紹介しました(2021年4月21日ブログ)。
そこでは、スマホが我々の身体やこころ、脳に与える様々な影響が書かれていました。
本書は、その『スマホ脳』の「ジュニア版」で、子供や若者にも読みやすいように書かれています。
何故、人の脳はスマホ依存になりやすいのか、といった脳の性質などが分かりやすく説明されており、その依存度を下げる方法が提案されています。
本書のあとがき(訳者あとがき)にも書かれている様に、本書は、
『けっして「スマホを使うのをやめましょう」とすすめる本ではなく、デジタル機器と上手に共存してゆくのが目的です。』
そして、
『・スマホの便利な機能は活用する。
・悪影響を及ぼす部分をきちんと理解して、気をつけられるようになる。
・身体も心も元気で、脳もしっかり働くようにする。そのために大切な"睡眠""運動""実際に人と会う"ための時間が足りなくならないようにする。』
といったことが薦められ、そのための方法が提案されています。
ですから、本書は、子供や若者だけでなく、現代の大人にこそ読んで実践して頂きたい内容だと思います。
ご興味のある方は、是非ご一読頂き、健康な身体と脳とこころ、そして生活を手に入れましょう!!
芝公園整骨施術院・鍼灸院・整体院
〜首、肩、腰の痛みや交通事故施術〜
スタッフ全員が経験豊富な国家資格者です♪
お気軽にお問合せ下さい♪♪
東京都港区芝2-8-13KITAハイム芝201
03-6400-3511
こんにちは。芝公園整骨治療院の藤本です。
『スマホはどこまで脳を壊すか』というちょっと怖いブログタイトルは、今回紹介する本のタイトルです(『スマホはどこまで脳を壊すか』榊浩平著/川島隆太監修/朝日新書)。
この衝撃的なタイトルの本の著者・榊先生は、ニン〇ンドーのゲームソフト『脳トレ』でお馴染みの東北大学・川島隆太先生の研究チームの方です。
川島先生も監修しています。
-225x300.jpeg)
これまでにも『スマホ脳』(アンデシュ・ハンセン著/新潮新書)など、スマホの使い過ぎが「脳」や「身体」に与える影響について警鐘を鳴らしている本を紹介してきました。
本書もまた『インターネットの使い過ぎは、学業成績や認知機能、さらには心の健康など、多くの悪影響があることが明らかになってきた』といったことが述べられています。
その中でも、私が特に面白いと思った内容は『つながる』ということについての考察です。
「心が通じる」とか「心がつながる」など、人が『「つながっている」と感じるとき、脳と脳も同期する」のだそうです。
人混みの中で多くの人が足並みを揃えて歩けるのは脳と脳が同期しているからだそうです。
また、サッカーなどのスポーツで選手同士が絶妙なタイミングで連携プレー出来ている時も、選手同士の脳と脳が同期しているのだ、ということを別の本で読んだことがあります。
脳の活動は電気信号を発しているので、それを計測することで脳の同期は調べられます。
川島研究室の実験結果では、なんと、『オンラインでは脳は「つながらない」』のだそうです。
それどころか、脳の状態としては『ひとりでボーっとしている状態と変わらない』のだそうです。
つまり、オンラインでは、情報の授受はできていますが、実は『「つながる」はずが孤独に』という状況を生み出しているようです。
それなのに、SNSなどでつながっていないと不安になる人が多い。
研究の結果としては、『オンライン・コミュニケーションは「社会的孤立」の解決にはつながらず、インターネット依存症を高め、逆に孤独を感じてしまい、将来の認知症のリスクを高めてしまう可能性があると考えられます』と結論しています。
やはり、『対面コミュニケーションには孤独感を減らす効果がありますが、SNS上のやりとりはその効果が薄い』ようです。
「つながる」はずのツールが、実はつながっておらず、むしろ孤独感を助長してしまって様々な将来のリスクを生んでいる。この事実いかがですか?
本書では、『すぐ始められる脱オンライン習慣のススメ』として、著者自らと編集者が行ったデジタル・デトックスについての報告もあります。
アナログ生活の良さを再認識してみるのも良いと思います。
インターネット依存症かな?と心当たりのある方。
インターネットの使用頻度が多いにも関わらず、インターネット依存症の自覚が無い方。
いずれにしても多かれ少なかれ現代人全員に当てはまる問題について書かれた本です。
ご興味を持たれましたら、是非ご一読ください。
芝公園整骨施術院・鍼灸院・整体院
〜首、肩、腰の痛みや交通事故施術〜
スタッフ全員が経験豊富な国家資格者です♪
お気軽にお問合せ下さい♪♪
東京都港区芝2-8-13KITAハイム芝201
03-6400-3511
こんにちは。芝公園整骨治療院の藤本です。
以前このブログで『スマホ脳』という本を紹介しました。
「スティーブ・ジョブズなどのIT業界のトップは自らの子供にはデジタル・デバイスを与えなかった」という事実と共に、
スマホが“脳”や“健康”に与える重大な影響について書かれていました(2021年4月21日のブログ参照)。
この本の反響を受けて、
“では、どうすれば良いの?”という問いに対するアンサーとして書かれたのが、
同著者による『最強脳』という本です。

『実は、この本の結論は一言で言えてしまいます。
運動をしよう—–そうすれば脳は確実に強くなる。』
日本語版の冒頭「日本の読者の皆さんへ」の中で、ハンセン先生がいきなりこう書いている通り、
この本の内容と結論はこの一点に尽きます。
ただ、大切なのは、“運動することによって、脳の中ではどのような変化が起きているか”、ということです。
前著『スマホ脳』では、スマホが“脳”や“身体”にどの様な影響を与えるかが書かれていましたが、
本書では「運動が子供や若者の脳にどのような影響を与えるかという知識を紹介」しています。
それと同時に「運動するモチベーション」が上がる様な知識の紹介もされています。
以前、『スマホ脳』を紹介した後に、『脳を鍛えるには運動しかない!!』という本も紹介しましたが(2021年5月11日ブログ)、
“身体”の健康のためだけでなく、“脳”のためにも、やはり“カラダを動かすこと”が一番良い様です。
本書でも、“カラダを動かすこと”は、
身体が強くなり、見た目もスッキリするだけでなく、
認知機能が高まり、発想力、記憶力、集中力も高まり、
気分も良くなって幸せな気分になり、
睡眠の質も改善されて、ストレスにも強くなる、と言っています。
皆さんがこの様にすこぶる健康になると、治療院としては少し困った面も出てくるかもしれませんが(笑)、
自身の為、是非、カラダを動かす習慣をつけて行きましょう!!
めざせ!健康長寿!!
芝公園整骨施術院・鍼灸院・整体院
〜首、肩、腰の痛みや交通事故施術〜
スタッフ全員が経験豊富な国家資格者です♪
お気軽にお問合せ下さい♪♪
東京都港区芝2-8-13KITAハイム芝201
03-6400-3511
こんにちは。芝公園整骨治療院の藤本です。
4月21日のブログで、スマホをはじめとするデジタル・モバイルが脳や健康に与える影響を紹介しました。
付き合い方を少し見直してみては?と、
スマホの怖い影響ばかりを列挙してしまいましたが(4月21日ブログ参照)、
今や仕事でもプライベートでも多用せざるを得ないデジタル・モバイル、
「じゃあ、どうすればいいの!?」と思った方もいたと思います。
そんな方に是非ご一読頂きたいのが、その名もズバリ!
『脳を鍛えるには運動しかない!』(ジョンJレイティー・著/野中香方子・訳/NHK出版)
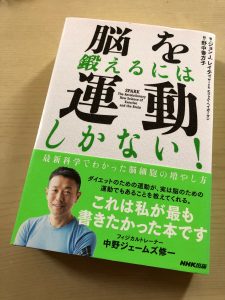
著者は「運動は脳の機能を最善にする唯一にして最強の手段だ」と強調しています。
この本の表紙裏の見出しには、
「運動すると35%も脳の神経成長因子が増える」
「運動で5歳児のIQと言語の能力には大きな差がでる」
といったことの他、
「運動することでストレスやうつを抑えられる」
「運動する人は癌にかかりにくい」
「運動を週に2回以上続ければ認知症になる確率が半分になる」
といったことが挙げられており、
注意欠陥障害や依存症などに与える運動の効果や、運動がホルモンの変化に関わって女性の脳に及ぼす影響なども述べられています。
しばらく前にNHKで放送された「シリーズ・人体」という番組の中でも、
筋肉や骨は、もはや単に身体を動かす為の運動器であるに留まらず、「臓器」として取り上げられていました。
書籍化されている『人体・神秘の巨大ネットワーク・臓器たちは語り合う』(丸山優二・NHKスペシャル「人体」取材班 /NHK出版新書)の中でも、
脂肪・筋肉や、骨、それら自体が、
脳や臓器の様にホルモン様のメッセージ物質を出して、
身体の様々な器官とネットワークして影響を与え、
運動すると大腸がんが予防できたり、
筋肉が出すメッセージ物質があらゆる生活習慣病の原因となる慢性炎症を抑える
などといった効果が期待できるという研究結果が報告されています。
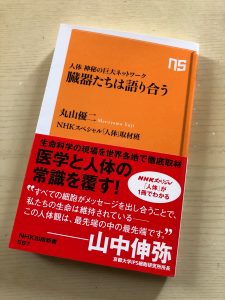
運動をして筋肉をしっかりと使ってあげることは、単に肉体の鍛錬のみならず、
脳や内臓、メンタル面に対しても、
そして様々な疾患の予防に対しても、
思っている以上に良い影響を及ぼすようです。
当院にはスポーツに詳しい者や、養生法、栄養学などに詳しい者など様々なスタッフが在籍しておりますので、
運動を行う上でのコンディショニングや運動後のケアにもぜひご利用ください。
めざせ!健康長寿!!
芝公園整骨施術院・鍼灸院・整体院
〜首、肩、腰の痛みや交通事故施術〜
スタッフ全員が経験豊富な国家資格者です♪
お気軽にお問合せ下さい♪♪
東京都港区芝2-8-13KITAハイム芝201
03-6400-3511
こんにちは。芝公園整骨治療院の藤本です。
「スマホ首(頚)」という言葉を聞いたことがある方は多いと思います。
当院でも、スマホをはじめとするモバイルの使い過ぎや、
使う時の姿勢が原因と思われる首肩や背部の凝り、腰痛、
或いは眼精疲労や頭痛で来院する方が少なくありません。
使用時の姿勢はもちろん、何よりも長時間の使い過ぎには気を付けなくてはならないことは
皆さん重々ご承知のこととは思います。
しかし今や無くてはならないデジタル・モバイル、
「そうは言っても、ついつい、なかなか手放せない」という方も多いのではないでしょうか?
しかし、このデジタル・モバイルの影響、
単に眼の疲労や首肩コリにとどまらず、“脳”への重大な影響がある、とするとどうでしょう?
少し前に話題となった『スマホ脳』(アンデシュ・ハンセン著/新潮新書)という本の中で、
スマホをはじめとするデジタル・モバイルが与える影響として、
記憶力や集中力、学力の低下、IQの低下といった影響が述べられています。
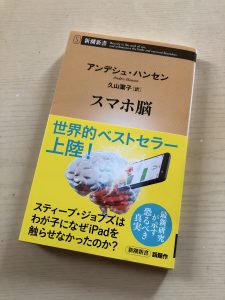
「バカになってゆく子供たち」という衝撃的な言葉や、
「スティーブ・ジョブズなどのIT業界のトップは自らの子供にはデジタル・デバイスを与えなかった」ということが述べられており、
子供だけでなく、「私たちのIQは下がっている」と、
大人の脳へも重大な影響が生じていることが論じられています。
また、依存症をはじめ、睡眠障害や鬱などの“心の病”など、
メンタルヘルスに与える影響についても多く述べられていて、
「スマホを頻繁に取り出して見る人ほどストレスを多く抱えていた」とか、
「不安(不安障害)とスマホの使用過多に相関性が見られた」といった研究結果が報告されています。
「ストレスと不安は本質的には体内の同じシステム(中略)の作動によって起きる」ので
「極端なスマホの使用が、ストレスと不安を引き起こす」というのです。
著者のアンデシュ・ハンセンは、同書のまえがきにて、
「人間は現代社会に適応するようには進化していない」としていて、
「人類史上、ここ数十年ほど急速にライフスタイルが変化したことはない。
しかも変わったのはデジタル関連の習慣だけではない。
これまで人類が体験したことのない種類のストレスが存在するようになった。
睡眠時間が減り、座っている時間が増えた。
そういうことは全部、脳にしてみれば未知の世界なのだ。
これがどういう結果を引き起こすのか―――
この本は、それに答えようとした結果だ。」
と述べています。
こうした急速なライフスタイルの変化に加えて昨今のコロナ禍による生活環境の変化とストレス!!
そんな中、便利なデジタル・モバイルの使用頻度(依存度)増加は、
ストレス解消や気分転換のアイテムとして役に立っていると思われる一方で、
実はコロナ禍のストレスをかえって増加させている可能性も・・・?
自らの健康(肉体的にも精神的にも)と脳、ひいては生命を守る為にも、
デジタル・デバイスとの付き合い方を是非一度見直してみてください。
それでも仕事でスマホを多用せざるを得ない方。
首肩コリや眼精疲労、頭痛の悪化防止や改善には
整体やマッサージでお役に立てる面があると思います。
自律神経の乱れには鍼やお灸も良いでしょう。
我慢せず、放っておかず、是非一度ご相談ください。
芝公園整骨施術院・鍼灸院・整体院
〜首、肩、腰の痛みや交通事故施術〜
スタッフ全員が経験豊富な国家資格者です♪
お気軽にお問合せ下さい♪♪
東京都港区芝2-8-13KITAハイム芝201
03-6400-3511