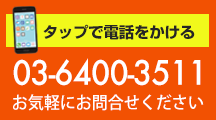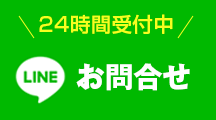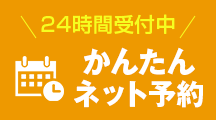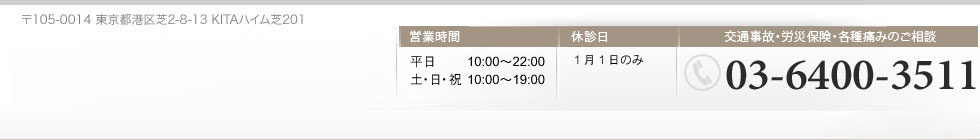Blog記事一覧 > だるさ | 芝公園・浜松町・赤羽橋・三田 芝公園整骨治療院の記事一覧
こんにちは。芝公園整骨治療院の藤本です。
ここのところ寒暖差が激しいですね。
体調を崩されている方も多いのではないでしょうか?
以前、このブログで『寒暖差疲労』を取り上げましたが、今回再度この『寒暖差疲労』を取り上げたいと思います(ネタの使い回しです!)。
『寒暖差疲労』は、前日との気温差や、一日の中での気温差が7度以上ある様な場合に、自律神経の調整機能が乱れて様々な身体の不調が出るものを指します。
症状としては、文字通りのだるさなどと同時に、肩凝りや頭痛、内臓症状では食欲不振や便秘・下痢などが現れることもあり、人によっては、めまいや不眠、イライラなどの気分の乱れも現れます。
自律神経である交感神経と副交感神経は、身体の活動モードと休息モード、体温の上昇と下降などを調整しており、ちょうどアクセルとブレーキの様な関係でバランスを取り合っています。
寒暖差が大きいと、気温の変化に身体を対応させようと、急激に何度もアクセルとブレーキをかけることになり、その調整がききにくくなってくるのです。
自律神経の調整機能は、普段の生活習慣(生活リズム)が大きくかかわることは言うまでもありません。
また、寒暖差に対する自律神経の調整機能については、筋肉量や運動習慣、発汗習慣も関係します。
筋肉は熱を発生させ体温を上げます。
一方、発汗によって体温は下がります。
運動と休息はアクセルとブレーキのメリハリをつけ、その調整機能を鍛えます。
在宅の時間が長く、空調(冷暖房)がきいた快適な空間の中であまり動かない。
その為に適度に心拍数が上がったり、発汗する機会も少ない。
となると、アクセルとブレーキの加減や、スイッチのオンとオフといった切り替えが鈍くなってゆきます。
そこに来て寒暖差が大きいと、自律神経の調整機能が追い付かず、上記の様な症状が現れる、という訳です。
対策としては、単純に、運動をする(適度に心拍を上げたり発汗する機会を持つ)、規則正しい生活を送る、空調(冷暖房)に頼り過ぎない、といったことが挙げられます。
つまり、普段から自律神経のアクセルを踏んだりブレーキをかけたり、スイッチを入れたり切ったり、ということを適度に、そして緩やかに行っておくことで、その調整機能を働かせて鍛えておくということです。
入浴で身体を温め発汗したり、首肩のストレッチを行うことも有効です。
生活習慣の改善だけでは追いつかなかったり、症状が強く出ている場合などは、針灸なども有効です。
針や灸の刺激は、滞った血流を改善したり、また、緊張を緩めたり、逆に働くべき機能を賦活したりといった効果があります。
季節の変わり目の体調不良にお悩みの方は、是非ご相談ください。
芝公園整骨施術院・鍼灸院・整体院
〜首、肩、腰の痛みや交通事故施術〜
スタッフ全員が経験豊富な国家資格者です♪
お気軽にお問合せ下さい♪♪
東京都港区芝2-8-13KITAハイム芝201
03-6400-3511
こんにちは。芝公園整骨治療院の藤本です。
冷房の出番が増えてきましたね。
冷え性の方は、冬の寒さ以上に手足の冷えが気になる季節かも知れません。
クーラーのきいたオフィスの中や電車の中で手足が冷えて、上着を羽織ったりひざ掛けをしたり、
場合によっては夏場でもレッグウォーマーが手放せない方もいらっしゃいます。
一方で、夏のクーラーの中でも、冬場の寒い中でも裸足で平気、手も温か。
むしろ足などは火照って熱く、
掛布団から足を出して冷えた壁に足を付けていないと眠れないという強者もいます。
冷え性の方からすれば、
『冷え性が無くて良いですね~』と羨ましく、健康体そのものに見えるかも知れません。
ところがちょっと要注意です!!
人間の体は冷気に触れたり、冷たい水に触れたりと、体を冷やす要因の中では、
四肢末端や体表の血管を収縮して熱の放散を抑え、
生命維持に大切な内臓や脳へと血液を還流し、
体温を維持しようとします。
つまり一定の条件下で手足が冷えてくるのは、ある程度は正常な反応です。
一方、いつも手足が温かという人は、
末端や体表の血管が開きっ放しで熱を放散し続けている状況で、
その分、体幹の深部、内臓が冷えている可能性があります。
つまり『隠れ冷え性』、『内臓冷え性』の可能性です。
意外と下痢しやすかったりお小水の回数が多かったりしませんか?
冷え性が無い(むしろ暑がり)と思って油断して体を冷やしていては将来大変なことになります。
また、手足の冷え性でも、
手足の両方が冷える「四肢末端冷え性」タイプの場合もあれば、
足だけが冷える「下半身冷え性」のタイプや、
足は冷えているけどむしろ上半身は暑がりの「冷えのぼせ」タイプの人などもいます。
こうした状況は、冷えている末端への血液循環が悪い状態や、熱のバランスが悪い状態。
末端が冷えているからといって、必ずしも内臓や体の中心まで冷えているとは限らない場合もあります。
そういった人が、「冷え性だから」と、胃腸や体を温める食事や補助食品で一生懸命「体質改善」を行っていてもあまり効果がないかもしれません。
場合によっては胃腸や内臓に熱がこもって他の熱症状が出ないとも限りません。
口内炎や吹出物がよく出る、便秘がちで便が乾いて硬い、のどがよく乾く……などの症状はありませんか?
胃熱や腸熱の症状かも知れません。
「冷え」は様々な体の不調を引き起こします。
体は冷えているより温まっている方が健康でいられます。
しかし、「冷え性」を考える場合、
体“全体”が冷えているのか?
体の中の寒熱のバランス(カラダの上下や、中心と末端のバランス)が偏っているのか?
その辺りをしっかりと見極めて行かなくてはなりません。
冷えと熱、陰と陽、虚と実。
自然界の状況は常に相反するものがセットとなって、そのバランスの中で成り立っています。
“どちらか一方”、“何か一つ”、ということはありません。
人間の体、健康状態、病気になっている状態にもまた同じことが言えます。
東洋医学や鍼灸医学では、
熱いから冷やす(熱を下げる)、冷えているから温める、ということ以外にも、
こもっている熱を冷えている部分に誘導して温めたり、
冷えている部分の冷気でオーバーヒートした熱をクールダウンしたり、と、
相反するものの間で互いに加減しあってバランスを良くする、という診方も大切にしています。
6月16日のブログで紹介した様に、鍼灸では、
一見症状とは関係の無い様な離れた場所に治療点(ツボ)があることなどは、
こうしたバランス観による部分があるのだと思います。
なかなか改善しない、原因が良く分からない、
そういった症状は、一度違う視点からの診方でお身体を診てみるのも良いかも知れません。
お悩みの症状のある方は、是非一度ご相談にいらしてください。
芝公園整骨施術院・鍼灸院・整体院
〜首、肩、腰の痛みや交通事故施術〜
スタッフ全員が経験豊富な国家資格者です♪
お気軽にお問合せ下さい♪♪
東京都港区芝2-8-13KITAハイム芝201
03-6400-3511